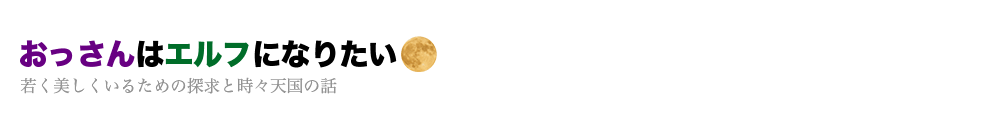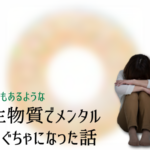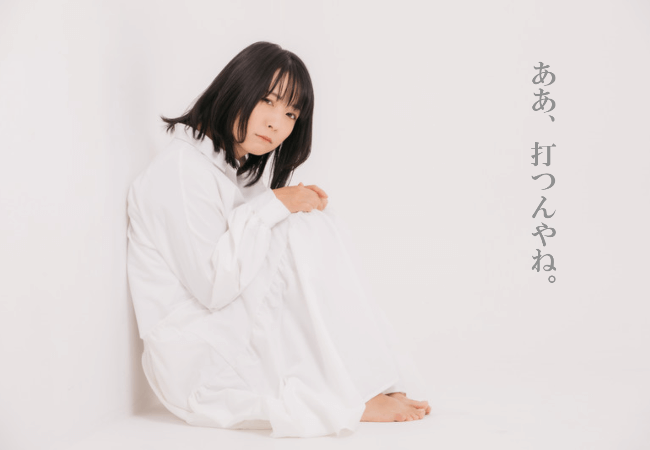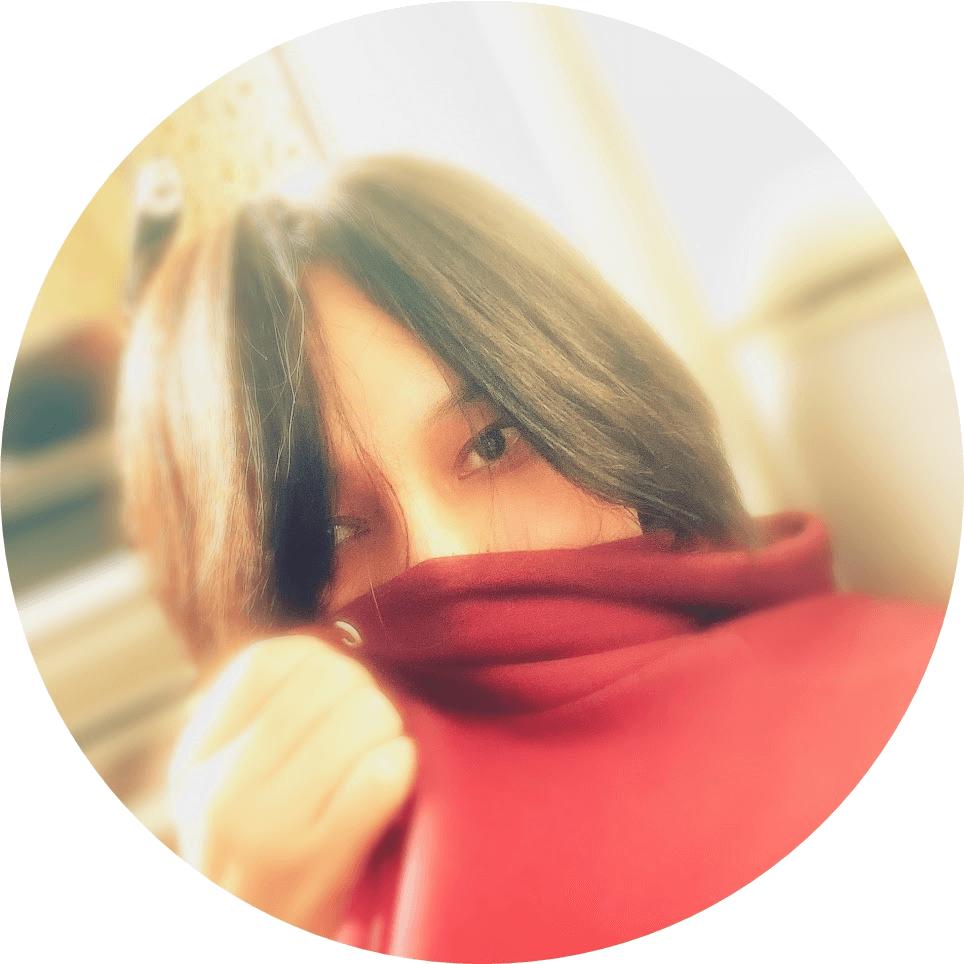肥満の原因は欧米化した食生活、と言われていますが、ちゃんと歴史を探ってみるとそうではないことがわかりましたのでご報告致します。
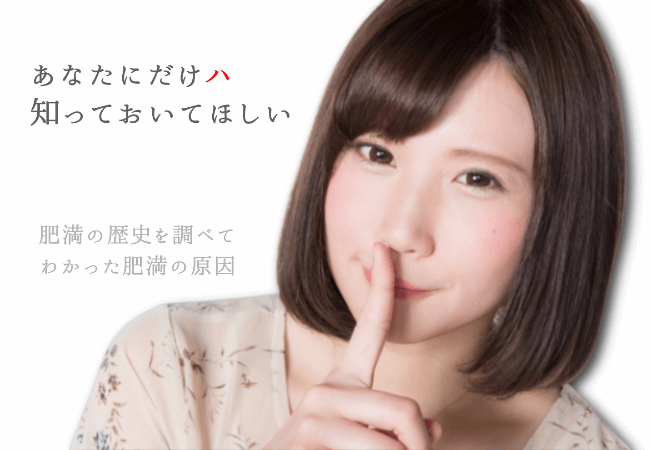
目次
肥満は1950年代から急速に増えた
1950年代に肥満病の震源地ことアメリカで突如、体重増加が目立つようになり、政府は記録をとりはじめました。
1950年代のアメリカといえば、第二次世界大戦で戦勝国になったことで、GDP成長率を見てもかなり景気は良かったようです。あと本土ほとんど攻撃されていませんし。
「豊かになって食生活が変わったから」
当然、私たちはそう考えますし、たしかそのように教わりました。
しかし、本当の原因は経済発展ではなくて、戦時中にありました。
肥満はDNAの遺伝ではない
たまに「肥満は遺伝」とか聞きますが、いやいやいや!たった半世紀の間で多くの人の遺伝子に突然変異が起きるとかミラクルすぎます。
ノルマンディー上陸作戦を皮切りに大流行したもの
ペニシリン(抗生物質)です。
1944年のノルマンディー上陸作戦で負傷した連合国軍の兵士たちに使われたのを皮切りに、奇跡的な回復の話が一般市民にも広まって大流行し、大量使用が始まりました。
そこから様々な抗生物質が開発されて、現在約100種類が出回っているとされています。
その結果、
- 1型糖尿病
- 多発性硬化症
- アレルギー
- 自閉症
- ノイローゼ(うつ病)
- 肥満
が増えました。
この2つの菌が殺菌されるとみるみる太る
- アッカーマンシア・ムシニフィラ
- ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)
この2つの細菌が少なくなると、食欲をコントロールするホルモンであるグレリンやレプチンへの感受性が鈍って食べ過ぎる傾向があらわれます。
腸の粘膜を厚くするアッカーマンシア
アッカーマンシアは腸壁表面の分厚い粘液層に存在しており、自分たちの住処を確保するために、腸壁細胞にはたらきかけて粘液の分泌を促進しています。
この腸内細菌のはたらきが弱まると、腸に微細な穴が開いてしまい、腸からLPS(リポ多糖)が血中に漏れ出し、炎症状態になります。
この状態になると、新しい脂肪細胞が作られず、既存の脂肪細胞にぎっしりと脂肪が溜め込まれるようになります。つまり、エネルギーの貯蔵システムが狂ってしまい、エネルギーをひたすら貯め込むようになるということです。
ベルギーのルーヴァンカトリック大学で栄養代謝学の教授をしているパトリス・カニ博士の行った実験。太ったマウスの一群にアッカーマンシアを加えた食事を与えてみたところ、マウスの体内でLPSの濃度が下がり、新しく健全な脂肪細胞が作られるようになり、体重が減った。さらにレプチンへの感受性が高くなり、食欲が減少した。(参照:「あなたの体は9割が細菌」アランナ・コリン著 矢野真千子訳)
レプチンは食欲を抑制するホルモンですので、LPSによる炎症によってレプチンへの感受性が悪くなると、満腹感が鈍り単純に食べすぎてしまうことになります。
アッカーマンシアを増やす栄養素
- DHA
- EPA
- 水溶性食物繊維
- ポリフェノール
- オリゴ糖
アッカーマンシアはこれらの栄養素をえさにして増殖します。逆に、これらが不足すると粘液を食べてしまうので要注意です。
食欲をコントロールするヘリコバクター・ピロリ
ピロリ菌は食欲を刺激するホルモンであるグレリンのレベルに応じて食欲をコントロールするはたらきをする共生菌です。
ニューヨーク大学のマーティンブレイザー博士の実験。退役軍人92人のうち、ピロリ菌をもつ23人に抗生物質を投与し、内21人の体内からピロリ菌を死滅させた結果、21人全員に体重の増加がみられた。BMI値は約5%(±2%)上昇した。他の退役軍人たちには体重の変化はみられなった。
彼らの体内では食欲を刺激するホルモンであるグレリンが食後に約6倍も増加し、食べても食べても満腹感を得られず、もっと食べたいと感じていることが判明した。
また、グレリンの値が高いほど腹部の脂肪が増えることがわかっている。(参照:「あなたの体は9割が細菌」アランナ・コリン著 矢野真千子訳)
ワシントン大学(セントルイス)のジェフリー・ゴードン博士は、現代人のピロリ菌の減少の原因を衛生的な生活環境と抗生物質の乱用と断じています。
ヘリコバクター・ピロリを増やす栄養素
- アミノ酸
- コレステロール
ヘリコバクター・ピロリはこれら栄養素をものすごく消費します。
とくにコレステロールについては胃の上皮細胞から得ていますので、コレステロールが不足すると胃が傷ついて胃潰瘍になります。
知る人は知っていた抗生物質が家畜を速く太らせるという常識
抗生物質で家畜の体内にいる特定の細菌を殺菌すると家畜がみるみる太るというのは畜産業界では常識です。
つまり、抗生物質によって生産効率が上がるのです。それも、生後なるべく早い段階で使うことで効果を最大限発揮します。
実際に、マウスを用いた実験で、
- 通常食
- 通常食+ペニシリン
- 高脂肪食
- 高脂肪食+ペニシリン
を与えたマウスをそれぞれ観察したところ、生後30週で体脂肪量は
- 通常食→約3g増加
- 通常食+ペニシリン→約3g増加
- 高脂肪食→約5g増加
- 高脂肪食+ペニシリン→約10g増加
のように変化しました。(参照:「あなたの体は9割が細菌」アランナ・コリン著 矢野真千子訳)
これが、抗生物質が体内の細菌組成を変え、その結果エネルギー貯蔵システムに影響を及ぼしエネルギーを溜め込みやすい体にする、ということを示しています。
ちなみにEUでは家畜の成長促進目的の抗生物質の使用を禁止しました。
おわりに
あとで知ったのですが、これ系の話題はあまり触れないほうが良いとされています。
ただ、私もこれらの情報を知ってから、日常生活のなかで「防御」という意識が持てるようになりましたので、あなたには共有したいと思った次第です。
①「どこ」で起こったのか?
②「いつ」から問題になっているのか?
③「だれ」がかかっているのか?
という視点で病気を調べていくと気づきがいっぱいあって捗ります。— rinrin (@riiiinpe) January 22, 2021
以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。